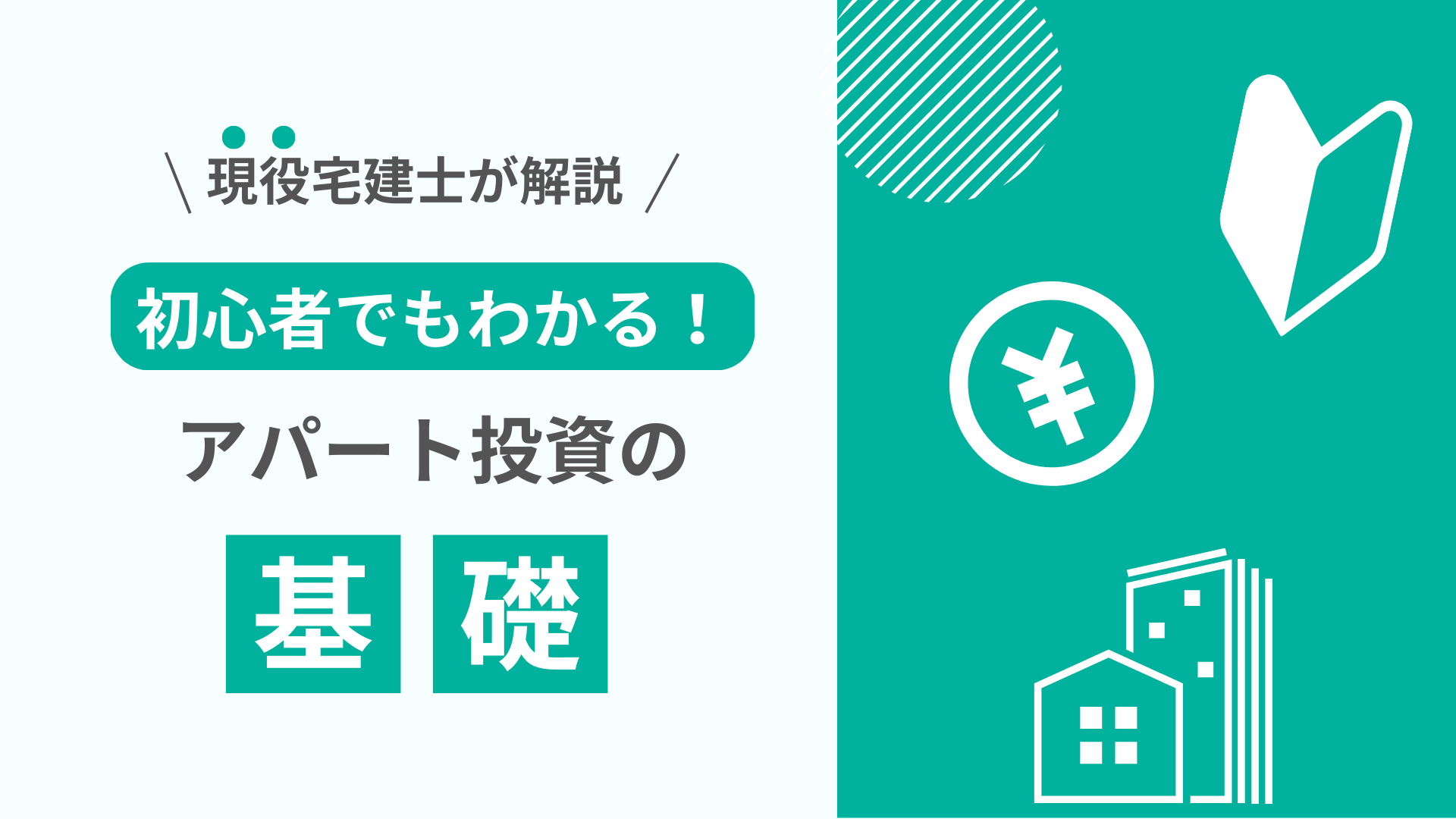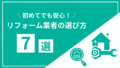アパート投資はうまく取り組めば、毎月数万・数十万円と家賃収入が得られる魅力的な投資です。
一方で、「金額が大きい投資だから簡単には手を出せない」と感じないでしょうか?
実際にアパート投資に取り組んだものの、失敗して破産に追い込まれる方がいるのも事実です。
こうした失敗の大半は、知識不足のままアパート投資を始めているのが原因です。
初心者の方でも、必要な知識を蓄えてから投資に臨めば、副収入が継続して入る状態を手堅く作り上げられます。
この記事では、宅建士として不動産会社に勤務する筆者が、アパート投資の基礎知識と初心者でも失敗を避けるための具体的なノウハウを解説します。
表からは見えにくい不動産会社の事情も交えて解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
また、動画でもアパート投資を学びたい方におすすめなのが、東京大学卒で不動産投資家の小原正徳さんのYouTubeチャンネルです。
自身の投資ノウハウや最新トレンドをわかりやすく解説しているので、初心者の方にもおすすめです。
こちらもぜひ一度ご覧ください。
小原正徳さんのYouTubeチャンネルはこちら
アパート投資とは
木造や軽量鉄骨造の共同住宅である賃貸アパートを一棟丸ごと所有し、家賃収入を得るのがアパート投資です。
「給与以外の副収入」「数百万円・数千万円の売却益」「家賃収入だけで生活」などのリターンが期待できます。
また、物件購入時に金融機関のローンを使えるのも大きな特徴です。
得た家賃収入をローン返済に充てるという「自己資金以外のお金を活用」し、効率よく資産形成を行えます。
アパート投資で収益が生まれる仕組み
アパート投資を始めると、どのように収益を得られるのでしょうか。
アパート投資の収益に関する主な考え方は以下の3つです。
① キャッシュフロー
② 売却益
③ トータルリターン
それぞれについて詳しく説明します。
① キャッシュフロー
不動産投資におけるキャッシュフロー(以降CF)とは、家賃収入からローン返済額や運営費を除いた手残りの利益を指します。
CFの計算式は以下のとおりです。
家賃収入ー(ローン返済額+運営費)=CF
※運営費には、管理にかかる費用・入居付けに必要な広告費・税金などを含みます。
具体的な数字を当てはめて計算します。
| 計 算 式 | 年間家賃収入600万円ー(年間ローン返済額410万円+年間運営費90万円) =年間CF 100万円 |
仮に5年間同じ状態でアパート投資を継続できた場合の合計CFは500万円です。
いわゆる「FIRE」と呼ばれる状態は、CFのみで生活ができる状態を指すことが多いです。
② 売却益
ここでの売却益とは、アパートの売却金額から「取得費用・ローン残債・売却時諸費用・税金」を差し引いた手残りの金額を指します。
計算式に表すと以下のとおりです。
売却金額ー(取得費用+ローン残債+売却時諸費用+税金)=売却益
※取得費用には、頭金・購入時の仲介手数料などを含みます。売却時諸費用には、売却時の仲介手数料・印紙税などが該当します。
こちらも具体的な金額を当てはめて計算してみましょう。
| 計 算 式 | 売却金額7,000万円ー(取得費用1,000万円+ローン残債5,000万円+売却時諸費用240万円+税金100万円) =売却益 660万円 |
売却で得た利益を次の物件の頭金にして、規模拡大を図れるのもアパート投資の魅力です。
③ トータルリターン
トータルリターンとは、「CFと売却益を合わせるといくらか」という考え方です。
CFと売却益を単体でみると、「そのアパートではいくら儲かったか」を正確に把握できません。
例えば、5年間の合計CFが+500万円でも売却益が−1,000万円では、その投資では損をしています。
反対に、売却益が−200万円でもCFが+1,000万円であれば、その投資はうまくいったといえます。
特にアパート投資では、目先のCFがプラスだと「儲かっている」という錯覚に陥りがちです。
「トータルで見た時に本当にプラスになるか」という視点を持ちましょう。
新築と中古の比較
アパート投資は大きく分けて、「新築」と「中古」の2種類があります。
また、新築の中でも以下の3種類に分かれます。
・建物が完成済みの「建て売り」
・建物が未完成だが土地と建築プランが決まっている「土地建物プラン付き」
・自分で土地の仕入れから建築まで取り仕切る「土地から新築」
それぞれを比較したものが以下の表です。
| 新築(建売) | 新築(プラン付き) | 新築(土地から) | 中古 | |
| 物件価格 | ✖️ | △ | ◯ | ◯ |
| 利回り※ | ✖️ | △ | ◯ | ◯ |
| 空室リスク | ◯ 〜 △ | ◯ 〜 △ | ◯ 〜 △ | ◯ 〜 ✖️ |
| 家賃下落リスク | ✖️ | △ 〜 ✖️ | ◯ 〜 ✖️ | ◯ 〜 △ |
| 建築リスク | ◯ | △ | ✖️ | ◯ |
| 融資の受けやすさ | ◯ | ◯ 〜 △ | ◯ 〜 ✖️ | △ |
| 始めるまでの期間 | ◯ | △ | ✖️ | ◯ |
| 修繕コスト | ◯ | ◯ | ◯ | △ 〜 ✖️ |
| 売却のしやすさ | △ 〜 ✖️ | △ | ◯ | △ 〜 ✖️ |
※利回りとは、投資した金額に対して、1年間で得られる利益の割合を指します。
例)100万円を投資して1年間で7万円の利益があれば、利回りは7%です。
「◯ 〜 ✖️」などのムラがあるのは、物件ごとに全く別の評価になることを表しています。
ここからは、新築と中古の2つに分けて細かく解説します。
新築アパート投資
新築アパート投資は、出来上がり前・出来上がって間もないアパートを購入して行う投資です。
外観や内装がキレイで、入居付けや融資付けをしやすいといったメリットがあります。
一方で、高値掴みをしやすい・入居がつくかわからない・家賃が下落しやすいといったデメリットもあります。
悪い物件でも融資がつきやすいからこそ、相場価格や賃貸需要を精査すべき投資といえるでしょう。
また、前述したように「建て売り」「土地建物プラン付き」「土地から新築」の3種類の投資法があります。
| 投資種別 | 特徴 |
| 建て売り | 建物が既に完成している状態から始める投資法です。 実際に建物を確認できるメリットはあるものの、不動産会社の利益が乗っている分、物件価格は割高傾向にあります。 大手不動産会社が販売していることも多いですが、会社のブランドだけで購入するのは危険です。 |
| 土地建物プラン付き | 購入する土地と建築プランが決まっている投資法です。 建て売り新築アパートと比べて建築リスクを負う分、物件価格が割安傾向にあります。 建築・収支プラン自体は出来上がっているので、比較的初心者でも取り組みやすい投資です。 |
| 土地から新築 | 土地の選定から施工会社の手配まで自分で行う投資法です。 建築での中間マージンがないので、最も安く投資物件を取得できます。 ただし、建築会社の倒産リスクなどの多くのリスクを負わなければなりません。 リスクや手間を取る分、リターンも高くなる投資といえます。 |
自身がどの程度のリスクや手間を取れるか精査したうえで、投資法を選択するとよいでしょう。
中古アパート投資
中古アパート投資は、既に入居が付いている中古物件を購入して行う投資法です。
利回りが高いなどのメリットがありますが、当然新築と比べた場合のリスクも存在します。
新築アパート比較したメリット・デメリットを表にまとめました。
| メリット | デメリット |
| ・物件価格が安い ・利回りが高い ・入居実績がわかる ・資産価値が下がりにくい | ・修繕コストがかかる ・融資がつきにくい ・売却が難しくなることがある ・設備が古く、入居付けが難しいケースがある |
新築アパートと比べると、修繕コスト・出口戦略などの事前シミュレーションがより重要になります。
他の不動産投資との比較
不動産投資にはアパート投資以外にもいくつか投資手法が存在します。
アパート投資以外の代表的な不動産投資法は以下の3種類です。
投資法① 区分マンション投資
投資法② 一棟マンション投資
投資法③ 戸建て投資
それぞれの投資とアパート投資を比較しながら解説します。
投資法① 区分マンション投資
区分マンション投資とは、マンションの1室を所有して賃貸に出す投資手法です。
一般的にマンションとは、鉄骨造・鉄筋コンクリート造(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の共同住宅を指します。
アパート投資と比較した際の主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| 取得価格が安いので買いやすく、売れやすい(流動性が高い)。 | 1室のため月々の家賃収入が少ない。月の収支がマイナスになる物件も多い。 |
| 築浅であれば満額近くローンが組めるので、少額の自己資金で始められる。 | 管理費や修繕積立金などを自分でコントロールできない。 |
| 駅近くで好立地の物件を買いやすい。 | 土地が共同所有のため、丸ごと手に入らない(更地にして売るなどできない)。 |
| アパートと比べて築年数が経っても建物の資産価値が落ちにくい。 | エントランスやエレベーターなどの共用設備の維持管理費が高い。 |
| 長期間のローンを組みやすい(月々のローン返済額が少ない)。 | 一棟投資に挑戦する際に、区分マンション投資のローン残債が、マイナス評価を受けることが多い。 |
区分マンション投資は金額が安くて始めやすいものの、儲かる物件を見つけやすいというわけではありません。
買えるから買うのではなく、「利益が出るから買う」という視点を持ちましょう。
投資法② 一棟マンション投資
一棟マンション投資は、マンションを一棟丸ごと購入して賃貸に出す投資法です。
区分マンション投資と違い、複数の部屋から家賃を得られ、土地も丸ごと手に入ります。
アパート投資と比較した際の一棟マンション投資のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| 購入時も売却時も長期間のローンを利用しやすい。 | 物件価格が高額で、多額の自己資金が必要(物件価格が数億円になることも多々あり)。 |
| 防音性や設備が優れているので、入居が付きやすい。 | 固定資産税などの税金が高額になりやすい。 |
| アパートと比べて築年数が経っても建物の資産価値が落ちにくい。 | エントランスやエレベーターなどの共用設備の維持管理費が高い。 |
| アパートよりも高額の家賃収入を得やすい。 | 物件価格が高額であるため、買い手が付きにくい。 |
アパートと比べてマンションは賃貸需要が高く、収益が安定しますが、取得金額の大きさがネックです。
必要な自己資金が1,000万円を超えることも多く、始めること自体が困難な投資といえます。
投資法③ 戸建て投資
戸建て投資とは、主に中古の戸建住宅を購入し、賃貸に出す投資手法です。
1戸のみの家賃収入ですが、安価で物件を取得しやすく、土地も全て取得できます。
アパート投資との比較は以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| 安価で物件を取得しやすい(物件によっては数百万円ほど)。 | 築古物件で投資を行うことが多いため、リフォーム・修繕費用が高額になりやすい。 |
| 土地の価値が残るため、資産価値が落ちにくい。 | 駅から遠い物件が多いので、賃貸需要の見極めが難しい。 |
| 主にファミリー層が入居のターゲットなので、入居期間が長くなりやすい。 | 築古戸建ての場合、管理や修繕の手間がかかりやすい。 |
| 建物や室内をメンテナンスなどを自由にコントロールできる。 | 築古の戸建は融資を受けにくい。 |
| 取得価格が安い分、高い利回りを期待できる。 | 空室時は家賃収入がゼロになる。 |
戸建投資は安価で物件を取得できて、高利回りの投資ができる反面、購入後の修繕や入居付けで手間がかかる投資といえます。
アパート投資のメリット9選
他の投資との違いなどを踏まえたアパート投資の具体的なメリットは以下の9点です。
メリット① 毎月の収入が増える
メリット② 空室リスクを分散できる
メリット③ 購入後は手間が少なめ
メリット④ インフレ対策になる
メリット⑤ 建物管理の自由度が高い
メリット⑥ レバレッジ効果がある
メリット⑦ 節税効果が高い
メリット⑧ 相続税対策になる
メリット⑨ まるごと土地が手に入る
メリット① 毎月の収入が増える
アパート投資では、毎月の家賃収入からローンや運営費を差し引いた金額が、手残りの収入として残ります。
毎月の収入が増えることで、以下のような恩恵を得られます。
・給料以外の副収入を得て、生活に余裕が生まれる
・年金+αの収入があることで、安心感のある老後生活を送れる
・ストレスフルな仕事を辞め、専業大家として家賃収入だけで暮らせる
そもそも毎月の使えるお金がプラスになるのは、他の投資ではあまりない特徴です。
例えば、積立投資では現金で金融商品を買うので、売却しない限り「今使えるお金」は減り続けます。
株式投資の配当金は、年1〜2回しか受け取れません。
同じ不動産投資でも、新築のワンルームマンション投資では毎月の収支がマイナスになることが多いです。
給料のように安心して使えるお金が毎月入るというのも大きなメリットといえるでしょう。
メリット② 空室リスクを分散できる
アパート投資では、1部屋だけでなく複数の部屋から家賃収入を得られます。
そのため、1室が空室でも他の部屋が埋まっていれば家賃収入は途絶えません。
ワンルーム投資や戸建投資では、1戸空室が出ると家賃収入はゼロです。
毎月のCFがプラスになるだけでなく、マイナスにもなりにくいのがアパート投資の魅力といえます。
メリット③ 購入後は手間が少ない
投資用アパートの購入後は、不動産管理会社に業務を委託することで、運営の手間を削減できます。
以下のような業務が管理会社に委託できる業務です。
・入居者のトラブル、クレーム対応
・清掃、クリーニング
・修繕費用の見積もり作成、業者の手配
・賃貸募集や案内、他の不動産会社とのやり取り
・契約書類の作成、説明・退去時の立ち会い
全ての業務を委託すると、オーナーのやることはほとんど無くなります。
ただし、委託料がかかるので、その分を含めた収支計算を行いましょう。
メリット④ インフレ対策になる
現物資産であるアパートは、インフレ(物価上昇)に強いのも大きな強みです。
物価が上昇すると、相対的に現金の価値は下がります。
頑張って貯金をしても、知らないうちに価値が目減りしているということです。
反対にアパートは、土地を始めとした現物資産で構成されているので、インフレ時に価値が上がる傾向にあります。
また、家賃も物価の1つなので、インフレ時に上昇しやすいです。
2025年現在、都内ではインフレに伴い、1Kやワンルームでも1年前より家賃が0.5万〜1万円ほど上がったケースがよく見られます。
貯金のみだとインフレに対して無防備なので、不動産を持つことを一つの選択肢として入れるとよいでしょう。
メリット⑤ 建物管理の自由度が高い
アパート投資のように一棟を丸ごと所有する投資では、オーナーの判断で自由に修繕やメンテナンスを行えます。
区分マンション投資の場合、毎月の管理費・修繕積立金の金額や共用部分の修繕時期を自分で決められません。
これは、マンションを複数のオーナーが所有をしているからです。
1人で丸ごと物件を保有できるアパート投資では、この制約がありません。
金銭的に余裕のない時期は修繕を控えめにしたり、メンテナンス時期をずらせたりします。
反対に共用設備にお金をかけることも可能です。
当初は無かった無料インターネット設備や宅配ボックスを導入し、家賃を引き上げるといった施策を打てます。
このように収支をコントロールしやすいのもアパート投資の魅力です。
メリット⑥ レバレッジ効果がある
不動産投資でのレバレッジ効果とは、少ない自己資金でも融資を活用することで、大きな投資成果を得られることを指します。
このレバレッジ効果が不動産投資における最大の魅力といっても過言ではありません。
例えば、1,000万円の自己資金で、以下の2パターンの投資用物件を購入したとします。
①1,000万円で利回り6%の物件を「1,000万円の自己資金のみ」で購入
②1億円で利回り6%の物件を「1,000万円の自己資金+9,000万円の融資(返済期間30年 金利2.0%)」で購入
それぞれのリターンを表で比較します。
| ①1,000万円全額自己資金 | ②1,000万円自己資金+9,000万円の融資 | |
| 年間家賃収入 | 1,000万円×6%=60万円 | 1億円×6%=600万円 |
| 年間融資返済額 | 0円 | 約400万円 |
| 年間収支 (家賃収入ー融資返済額) | 60万円−0円=+60万円 | 600万円–400万円=+200万円 |
| 自己資金に対する利回り | 60万円÷1,000万円=6% | 200万円÷1,000万円=20% |
融資を活用したことで、200万円−60万円=年間+140万円収益、20%−6%=年間+14%の自己資金に対する利回りを得られています。
メリット⑦ 節税効果が高い
他の不動産投資と比べて、節税効果が高いのもアパート投資の特長です。
節税効果とは、「会計上の赤字」を給与所得などと合算し、所得税や住民税を減額する効果を指します。
例えば、会社員で年収が1,500万円の方の年間所得税・住民税は合わせて約330万円です。
仮にアパート投資で、会計上の赤字を年間500万円計上できると、年間所得税・住民税は約140万円まで下がります。
このケースでは、330万円−140万円=年間190万円もの節税効果があるということです。
アパート投資における代表的な会計上の赤字として「減価償却費」が挙げられます。
減価償却とは、建物の価値が下がった分を赤字として計上できるという税法上のルールです。
つまり、実際の支出を伴うことなく赤字を捻出できるということです。
税法上における建物価値の下落幅は、「法定耐用年数」という基準で算出されます。
法定耐用年数とは、新品の建物や設備を通常使用できる期間として法的に定められた年数のことです。
法定耐用年数は、建物の種類や築年数によって変動し、築年数が経っているほど減価償却費として毎年計上できる金額は大きくなります。
アパートの場合、法定耐用年数が短いので減価償却費を大きく計上できます。
以下が建物種別ごとの法定用年数です。
| 建物種別 | 法定耐用年数 | |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 | |
| レンガ・ブロック造 | 38年 | |
| 鉄骨造 | 厚み4mm 超え | 34年 |
| 厚み3~4mm(アパート) | 27年 | |
| 厚み3mm以下(アパート) | 19年 | |
| 木造(アパート) | 22年 | |
例えば新築木造アパートの場合、「建物価格に対して毎年1/22ずつ減価償却費を計上できる」ということです。
仮に建物価格5,000万円で築23年の木造アパートを投資用で購入したとします。
法定耐用年数オーバーの建物は4年で全額を減価償却できます。
1年にならすと、1,250万円が赤字計上可能です。
年間家賃収入が700万円だとしたら、減価償却費だけで1,250万円−700万円=年間550万円の節税効果があります。
さらに、建物分のローン金利なども赤字の金額に加えられます。
納税額の多さに悩む高所得者にとって、アパート投資の節税効果は非常に魅力的です。
ただし、売却時に減価償却費として計上した金額は、アパートの取得費から除外されます。
売却時の税金計算の元となる売却益は、売却価格から取得費などを差し引いて計算します。
つまり、売却時の税金が高くなる可能性があるということです。
目先の節税効果だけでなく、出口まで見据えた税金計算をしましょう。
メリット⑧ 相続税対策になる
所得税や住民税以外に、アパート投資には相続税への節税効果があります。
なぜなら、現金よりアパートの土地・建物の方が相続税評価額が大きく下がるからです。
例えば、相続税対策のため1億円(土地5,000万円・建物5,000万円)のアパートを購入したとします。
まず、現金を土地と建物に変えることで、相続税評価額を土地は約80%・建物は約70%まで下げられます。
これは、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」という取得費とは違う金額で査定されるからです。
※路線価は取得価格の約80%、固定資産税評価額は取得価格の約70%で算定されます。
| 計 算 式 | 土地:5,000万円×80%=4,000万円 建物:5,000万円×70%=3,500万円 |
相続対象が賃貸用のアパートだと、評価額から土地は約20%、建物は約30%の金額がさらに差し引かれます。
| 計 算 式 | 土地:4,000万円−(4,000万円×20%)=3,200万円 建物:3,500万円−(3,500万円×30%)=2,450万円 |
最終的に、相続評価額は3,200万円+2,450万円=5,650万円となりました。
現金と比べると、1億円−5,650万円=4,350万円も相続税評価額を下げられます。
仮に、相続人が配偶者なし・子ども2名だった場合の相続税を考えましょう。
・現金1億円の場合:相続税は約770万円
・アパート1億円(土地5,000万円・建物5,000万円)の場合:相続税は約145万円
770万円−145万円=625万円もの節税効果があるという計算結果になりました。
以上のように、アパート投資では大幅な相続税の節税効果が期待できます。
メリット⑨ まるごと土地が残る
長期的な資産形成において土地が手に入るということもアパート投資のメリットです。
例えば、建物の資産価値は年々下がりますが、土地は年数の経過に伴い価値が下がるわけではありません。
好立地の物件を購入できれば、価値の維持や上昇を期待できます。
また、区分マンション投資の場合は、土地の所有権は全部屋のオーナーとの共有名義です。
そのため、自分自身にはわずかな土地の持分しかありません。
そのため、建物が老朽化すると資産価値が大きく下がり、土地を活用したいと思っても自分の意思だけでは何もできません。
一方でアパート投資であれば、土地は丸ごと自分の所有物です。
古くなった建物を建て替えたり、更地にして売るなど自由に活用できます。
アパート投資のデメリット9選
アパート投資にはメリットだけではなく、当然デメリットやリスクが存在します。
デメリットへの理解は、メリット以上に重要なこともあります。
主なデメリットは以下の9つです。
デメリット① まとまった自己資金が必要
デメリット② ローン審査が厳しい
デメリット③ 空室リスクがある
デメリット④ 家賃下落リスクがある
デメリット⑤ 修繕リスクがある
デメリット⑥ 簡単に売買できない
デメリット⑦ 築年数が経つと融資が付きにくい
デメリット⑧ 逆レバレッジが発生する可能性がある
デメリット⑨ 良い物件を買うまでに行動量が必要
デメリット① まとまった自己資金が必要
アパート投資は融資を使って物件は買えるものの、頭金が必要になることが大半です。
融資を出す条件として物件価格の5~10%、高いと20%以上の自己資金を銀行から求められることがあります。
7,000万円のアパートを購入する際に、10%の自己資金が必要だとしたら、700万円を用意しなければなりません。
加えて、仲介手数料が物件価格の3%+6万円+消費税かかるとして、237.6万円が必要です。
合計すると、1,000万円弱の自己資金が求められます。
このように多額の自己資金を準備できなければ、アパート投資を始められません。
デメリット② ローン審査が厳しい
まとまった自己資金があったとしても、アパートを購入できる金額を銀行から借りられるとは限りません。
ローンの審査時には、収入の高さや安定性なども見られるからです。
例えば、銀行の融資基準が「大企業に勤めていれば年収の10倍・アパート価格の最大95%までは融資可能」だとします。
この銀行では、大半の個人事業主の方が好条件で融資を受けるのは難しいでしょう。
また、銀行によって融資条件は異なるので、1つの銀行がダメなら複数の銀行を回る労力が必要です。
逆の見方をすると、銀行を回る努力などができた分、融資チャンスが広がるともいえます。
デメリット③ 空室リスクがある
メリットの解説で、空室リスクを分散できると伝えましたが、空室リスク自体は無くなりません。
入居付けができなければ家賃収入は減り、借入で物件を購入している場合は返済に苦しみます。
常に入居率100%であることは、基本的にあり得ません。
アパートの立地などによって、一定の空室率を考慮した収支計算が必要です。
例えば、首都圏であれば入居率95%・郊外であれば90%などで計算し、採算の取れた収支になっているか確認します。
不動産会社の提示する収支計算が満室想定の場合は、収支計算が間違っているかもしれません。
デメリット④ 家賃下落リスクがある
不動産投資では、築年数が経つにつれて家賃が下落していく傾向にあります。
少し古いデータですが、東京23区の賃貸マンションの家賃下落率を算出したのが以下の表です。
| 築年数 | 年間家賃下落率(広さ18㎡以上30㎡未満の部屋) |
| 新築〜築10年 | 約1.1% (10年で約11%の家賃下落) |
| 築11年〜築20年 | 約0.6% (10年で約6%の家賃下落) |
| 築20年以降 | 下げ止まる |
参照:三井住友トラスト基礎研究所 経年劣化が住宅賃料に与える影響とその理由
上記表を参照すると、新築から10年で10%以上家賃が下落することがわかります。
新築時の賃料が10万円なら10年後は9万円以下に、8部屋のアパートなら月の収入が8万円以上も下がる恐れがあるということです。
特に、新築で相場より高めの家賃設定のアパートを購入する際は、賃料の下落を加味して収支計算をしなければなりません。
築浅物件なのに、不動産会社から提示された収支計算が、家賃の下がらない想定の場合は注意しましょう。
デメリット⑤ 修繕リスクがある
アパートを所有していると、築年数が経つにつれ設備の修繕や交換が必要になります。
そのため、修繕のための十分な自己資金を手元に残しておくことが重要です。
修繕費用の目安や時期を以下の表でまとめました。
◾️主な室内設備の交換費用の目安
| 設備 | 費用目安 | 交換時期の目安 |
| フローリング | 1万円〜3万円/㎡ | 15〜20年 |
| 壁紙 | 1,000円〜1,500円/㎡ | 10年 |
| 網戸 | 1,000円〜5,000円 | 5〜10年 |
| キッチン一式 | 10万円〜50万円 | 15〜20年 |
| ガスコンロ | 3〜5万円 | 10年 |
| 給湯器 | 10万円〜25万円 | 10年 |
| ユニットバス | 50万円〜80万円 | 15〜20年 |
| 浴室乾燥機 | 10万円〜20万円 | 10年〜15年 |
| トイレ(本体ごと) | 5万円〜20万円 | 10年〜15年 |
| トイレ(便座) | 3万円〜10万円 | 10年〜15年 |
| エアコン(1台) | 5万円〜12万円 | 10年 |
| 独立洗面台 | 5万円〜10万円 | 10年〜15年 |
| モニター付きインターホン | 5万円 | 10年〜15年 |
◾️共用部分を含めたアパート修繕費用の目安
| 時期 | 修繕箇所 | 費用(1戸あたり) |
| 5〜10年目 | ベランダ・階段・廊下(塗装) 室内設備(修理) 排水管(高圧洗浄等) | 約7万円 |
| 11〜15年目 | 屋根・外壁(塗装) ベランダ・階段・廊下(塗装・防水) 給湯器等(修理・交換) 排水管(高圧洗浄等) | 約52万円 |
| 16〜20年 | ベランダ・階段・廊下(塗装) 室内設備(修理) 給排水管(高圧洗浄等・交換) 外構等(修繕) | 約18万円 |
| 21〜25年 | 屋根・外壁(塗装・葺替) ベランダ・階段・廊下(塗装・防水) 浴室設備等(修理・交換) 排水管(高圧洗浄等) | 約80万円 |
| 26〜30年 | ベランダ・階段・廊下(塗装) 室内設備(修理) 給排水管(高圧洗浄等・交換) 外構等(修繕) | 約18万円 |
▶︎新築から30年で1戸あたり約174万円の修繕コスト
物件価格だけでなく、修繕費用も加味したうえで物件選定を行いましょう。
デメリット⑥ 簡単に売買できない
基本的にアパート1棟あたりの物件価格は高額であるため、株式のように簡単に売買を行えません。
そのため、まとまったお金が欲しい時に、アパートをすぐ現金化できないのがネックです。
短期で収益を狙いたい方には向かない投資といえるでしょう。
反対に、簡単に売買ができない分、株価のように乱高下しないというメリットがあります。
家賃収入を得ながら売りに出し、チャンスがあれば売るといったスタンスがおすすめです。
デメリット⑦ 築年数が経つと融資が付きにくい
中古アパート投資の弱点として長期間の融資が付きにくい点が挙げられます。
法定耐用年数の長さに基づき、融資可否や融資期間が決まることが多いからです。
アパートの場合、RC造のマンションと比べて法定耐用年数が短いので、長期融資のハードルが上がります。
築年数が経つと法定耐用年数も短くなるので、長期融資を受けるのがより難しくなります。
これは購入時だけでなく、売却時にも影響があるので注意が必要です。
自分は30年ローンでアパートを買えたとしても、10年後は同じ条件で購入希望者がローンを組めるとは限りません。
融資期間が短くなったり、金利が上がったりすると購入候補から外れやすくなります。
売却を前提にアパートを買う場合は、出口の融資条件も加味しなければなりません。
デメリット⑧ 逆レバレッジが発生する可能性がある
レバレッジ効果は不動産投資の最大の魅力の1つと前述しましたが、適切に活用できないとむしろマイナスに働きます。
自己資金のみで投資をした時より、マイナスになる状態を「逆レバレッジ」といいます。
主に金利が高い・ローン期間が短いことで逆レバレッジになりがちです。
レバレッジ効果の説明時と同じく、自己資金が1,000万円の場合の投資シミュレーションをします。
①1,000万円で利回り6%の物件を「1,000万円の自己資金のみ」で購入
②1億円で利回り6%の物件を「1,000万円の自己資金+9,000万円の融資(返済期間20年 金利2.5%)」で購入
それぞれのリターンを表で比較します。
| ①1,000万円全額自己資金 | ②1,000万円自己資金+9,000万円の融資 | |
| 年間家賃収入 | 1,000万円×6%=60万円 | 1億円×6%=600万円 |
| 年間融資返済額 | 0円 | 約570万円 |
| 年間収支 (家賃収入−融資返済額) | 60万円−0円=+60万円 | 600万円–570万円=+30万円 |
| 自己資金に対する利回り | 60万円÷1,000万円=6% | 30万円÷1,000万円=3% |
自己資金のみで投資をした時より、リターンが小さくなってしまいました。
こうした逆レバレッジに注意して収支計算を行いましょう。
デメリット⑨ 良い物件を買うまでに行動量が必要
株式などと違い、投資用アパートは一点ものなので、良い物件を見つけたとしても買えるとは限りません。
めげずに日々良い物件を探し続ける行動量やメンタルが必要です。
具体的には以下のような行動を継続する必要があります。
・投資用不動産のポータルサイトで(楽待や健美家など)相場感を養う
・投資用アパートを取り扱う不動産会社とのコネクションを作る
・融資をしてくれる銀行の開拓する
・最新情勢や不動産投資ノウハウなどの勉強する
・自己資金を増やすための倹約や勤労をおこなう
決して楽な道のりではない分、自身の行動量で差別化を図れる投資とも言えます。
アパート投資を始めるのにいくらかかるのか?
デメリットの項目でも触れましたが、アパート投資を始めるには初期費用がかかります。
金額のおおよその目安としては、物件価格の約15%ほどです。
費用の内訳を以下の3項目に分けて解説します。
費用① 頭金
費用② 諸費用
費用③ 税金
費用① 頭金
アパートを購入する際には、ローンを組むことが大半ですが、物件価格に対して満額のローンが出るのは稀です。
アパートの資産性や収益性を証明できても、物件価格の5~10%は頭金を求められる傾向にあります。
仮に7,000万円のアパートだとしたら、少なくとも350万円〜700万円は頭金を求められるイメージです。
築年数が経っている・自身の年収が700万円以下などに該当すると、さらに多くの頭金が必要になることもあります。
費用② 諸費用
仲介などで不動産会社から投資用アパートを購入する際には、物件価格以外にかかる諸費用があります。
代表的な諸費用と金額の目安をまとめました。
| 諸費用の項目 | 金額の目安 |
| 仲介手数料 | 上限は物件価格3%+6万円+消費税。 7,000万円のアパートなら最大237.6万円。 |
| 火災保険料 | 物件やプランによって大きく変動します。 1年平均でおよそ年5万円〜15万円ほど。 |
| 司法書士報酬 | 約10~15万円。 |
| ローン手数料 | 金融機関ごとに異なります。 定率型:借入金額の1%~3%ほど。 定額型:3~10万円ほど。 |
| ローン保証料 | 金融機関ごとに異なります。 一括前払い(外枠方式):借入金額×2%ほど。 金利に上乗せ(内枠方式):金利に0.2%~0.3%ほど上乗せ。 |
費用③ 税金
アパート購入するとかかる主な税金は、以下の4つです。
| 税金の項目 | 金額の算定方法 |
| 不動産取得税 | 課税標準額(土地は時価の約7割程度、中古建物は再建築価格の2~8割程度、新築建物は請負金額の5~6割程度)×税率で算出します。 税率は4%(令和9年3月31日まで軽減税率が適用され3%)。 土地が宅地(住宅用の土地)であれば、課税標準額を1/2に減額します。 さらに、①②のいずれの高い方の金額を土地の税額から控除可能です。 ①45,000円 ②土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×住宅の取得持ち分×3% 7000万円の中古アパートであれば、約100万円の税金が発生します。 不動産を取得してからおおよそ4~6ヶ月後に通知書が届きます。 |
| 登記費用(登録免許税) | 課税標準額×税率で算出します。 ▼税率 ・土地(所有権移転登記)=2.0%(令和8年3月31日までは軽減税率適用で1.5%)・新築建物(所有権保存登記)=0.4% ・中古建物(所有権移転登記)=2.0%・借入れをする際(抵当権設定登記)=0.4% 7,000万円の中古アパートであれば、約100万円の登記費用が発生します。 |
| 印紙代(印紙税) | 物件の金額によって変動します。 令和9年3月31日まで軽減税率を適用可能です。 1千万円を超え5千万円以下:2万円(軽減後 1万円) 5千万円を超え1億円以下:6万円(軽減後 3万円) 1億円を超え5億円以下:10万円(軽減後 6万円) |
| ローン手数料 | 金融機関ごとに異なります。 定率型:借入金額の1%~3%ほど。 定額型:3~10万円ほど。 |
| 固定資産税・都市計画税の精算 | 売主が先に支払った1年分の固定資産税や都市計画税のうち、不動産を取得した日以降の分は買主が精算します。 |
以上のように、アパート購入時には高額な初期費用が求められるため、十分な資金を蓄えた上で物件選定を行いましょう。
投資用アパートの保有中にかかる費用
アパート投資を行う際は、初期費用だけでなく物件の運営費も発生します。
運営費の目安としては、家賃収入の20~30%が一般的です。
主な運営費の項目は以下のとおりです。
| 運営費の項目 | 費用の詳細 |
| 広告料 | 入居付けをしてくれた不動産会社に支払う報酬。 広告料が多いほど、賃貸仲介会社が積極的に入居付けをしてくれます。 賃貸需要が高いエリアでは広告料が0円のケースもありますが、賃料の0.5~2.0倍の金額で設定することが多いです。 |
| 管理費 | 共用部分の清掃費や電気・水道代など。 |
| 修繕費 | デメリット⑤ 修繕リスクを参照 |
| 税金 | 固定資産税、都市計画税が主に該当します。 固定資産税は課税標準額×1.4%の金額都市計画税は課税標準額×0.3%の金額。 |
| ローン保証料 | 融資を受けて物件を購入した際に発生します。 |
運営費の計算が不十分だと、正確な収益性を把握できません。
「出費の多いアパートを買ってしまった」と後悔しないようにシミュレーションしましょう。
アパート投資はどんな人におすすめか?
アパート投資にも向き・不向きが存在します。
以下の5つの要件に当てはまる方にアパート投資はおすすめです。
要件① 高年収・安定した職業の方
要件② まとまった現金や金融資産をお持ちの方
要件③ 高額な相続税対策が必要な方
要件④ 細かいシミュレーション・大量行動ができる方
要件⑤ 賃貸需要のある土地を所有している
要件① 高年収・安定した職業の方
高年収・安定した職業の方は、銀行から好条件で融資を受けやすいため、アパート投資に向いています。
高年収の目安としては年収700万円以上で、年収は高いほどローン審査では有利です。
安定した職業とは、以下のようなお仕事をされている方を指します。
・大手企業の会社員
・公務員
・医師や弁護士などの師士業
年収・職業の要件を満たすことで、低金利・長期間・高額の融資を受けられる可能性が高まります。
また、勤続年数が3年以上であることも審査にプラスに働く要件です。
転職をすると、勤続年数がリセットされるので注意しましょう。
要件② まとまった自己資金・金融資産のある方
自己資金がどの程度あるかもアパート投資においては重要なポイントです。
銀行は貸したお金がきちんと返済されるか(返済能力)を融資審査時に重視します。
返済能力は年収に加え、どの程度自己資金や金融資産を保有しているかで判断されます。
年収が1,000万円で自己資金が500万円の状態より、年収500万円でも自己資金で1億円の状態の方が一般的に銀行評価は高いです。
つまり、多くの自己資金や金融資産を持っていることで、融資条件が良くなりやすいということです。
他にも自己資金が多いと以下のような強みがあります。
・必要な自己資金の高さが原因で、競合が少なくなっている物件を買える。
・万が一のトラブルにも自己資金の多さでカバーできるので、投資の安定感が増す。
・アパートの買い増しをしやすい。
目安として自己資金が2,000万円・年収が700万円以上あると、アパート投資で良いスタートを切りやすいです。
要件③ 高額な相続税対策が必要な方
現金で1億円など、高額な相続の可能性がある方にもアパート投資がおすすめです。
基本的に不動産を活用した相続税対策が最も節税効果が高いからです。
別の相続税対策として①年110万円までの贈与、②生命保険の活用があります。
| 相続対策の種類 | 詳細 |
| ①贈与 | 年間1人につき110万円までであれば、贈与税や相続税がかからない税法上の仕組みです。 大きな節税効果を生むには、数十年以上の期間を要します。 |
| ②生命保険 | 死亡時の生命保険としてお金を相続すれば、1人500万円まで非課税で受け取れる仕組みです。 相続する相手が少ないと、大きな節税効果は期待できません。 |
前述したように現金1億円をアパートに変えて相続した時には、相続税評価額を数千万円単位で減らすことができます。
およそ1億円以上の相続対策が必要となった際には、アパート投資を選択肢の一つに入れると良いでしょう。
要件④ 細かいシミュレーション・大量行動のできる方
アパート投資で成果を出すには、細かい収支計算ができなければなりません。
残念ながら簡単に見つける投資用物件の大半は、リスクに対するリターンが見合っていないからです。
不動産会社の収支計算では儲かりそうな物件でも、自分で計算し直すとマイナスになることは少なくありません。
・空室率を踏まえた家賃収入
・賃料の下落・運営費や税金
・利益の出るローン期間や金利
・物件価格の相場
以上のように、計算しなければならない項目は多岐に渡ります。
細かい投資シミュレーションができる人にとっては、結果をコントロールしやすい投資ともいえます。
また、シミュレーション力に加え、物件探しや銀行開拓など行動力も必要です。
良い物件は奪い合いなので、簡単には巡り合えません。
瞬時にアパートの収支計算ができる状態で、大量に行動してようやく優良物件が購入できます。
要件⑤ 賃貸需要のある土地を所有している
すでに賃貸需要のある土地をお持ちの方は、建物にかかる費用だけでアパート投資を始められます。
初期費用やローン返済額などが少ない分、損をしにくい状態で投資を行えるということです。
土地自体を担保にして、建築費用分のローンも組めるので、手出しのお金を大きく抑えられます。
土地の賃貸需要に関しては、近隣の不動産賃貸仲介会社に「賃貸募集をお願いする前提」で聞くのがおすすめです。
・そもそも賃貸需要はあるか
・どれくらいの家賃相場か
・どんな間取りが人気か
・入居付けにどれくらいの期間がかかるか
また、賃貸仲介会社が忙しい時間帯は十分に回答をしてもらえない可能性があります。
平日昼過ぎ〜夕方までの仕事が落ち着いていそうな時間に、電話などで聞くのがおすすめです。
そのほかには、LIFULL HOME’Sの「賃貸需要ヒートマップ」でも賃貸需要を把握できます。
赤いエリア内であれば、インターネット上でよく賃貸物件検索がされています。
ツールもうまく活用して賃貸需要を確かめましょう。
アパート投資の始めるまでの8ステップ
続いて、アパート投資を始めるまでの時系列について解説します。
基本的なステップは以下のとおりです。
| 流れ | 詳細 |
| Step1.目的を定める | まずは、アパート投資をする目的を定めます。 ・副収入を得る ・専業大家になる ・相続対策をする など目的が違うだけで選ぶべき物件も変わります。 |
| Step2.物件を探す | ポータルサイトを見る、不動産会社から紹介を受けるなどして物件を探します。 |
| Step3.買い付けを入れる | 物件の内覧や現地調査を行ったら売主に対して買い付け証明書を提出します。 買い付け証明書は物件購入の意思や希望条件を伝えるための書類です。 提出段階で物件の購入は確定しません。 |
| Step4.銀行の事前審査をかける | 銀行から融資を受けるために事前審査を受けます。本人確認書類や事業計画書の提出などを行います。 |
| Step5.売買契約を結ぶ | 事前審査を通過し、資金調達の目処が立ったら不動産売買契約を結びます。 手付金の支払いもこのタイミングで行われることが多いです。 |
| Step6.銀行の本審査を受ける | 売買契約を締結したら銀行の本審査が行われます。 より詳細な物件の担保価値や自身の返済能力・健康状態などがチェックされます。 審査期間は、2週間から1ヶ月ほどです。 |
| Step7.管理会社の選定 | 物件の管理や賃貸募集を行う管理会社を決定します。 |
| Step8.物件の引き渡し | 金銭貸借契約を締結し、全ての決済が完了したら物件が引き渡しされます。 |
スムーズに手続きが進んだ場合、中古アパートは事前審査から1ヶ月半〜2ヶ月ほどで物件を取得できます。
新築アパートの場合は、未完成の物件もあるので、取得までにかかる期間は大きく異なります。
アパート投資で失敗しないための5つのポイント
こちらでは、アパート投資で致命的な失敗を防ぐために注意すべきポイントを解説します。
ポイントは以下のとおりです。
Point 1. 先に自分が受けられる融資条件を把握する
Point 2. 高値掴みをしない
Point 3.エリアの賃貸需要や災害リスクを正確に調査する
Point 4.違法建築物でないか確かめる
Point 5.ランニングコストを十分に加味する
Point 1. 先に自分が受けられる融資条件を確認する
いざアパート投資を始めるとなると、物件探しから始める方が大半でしょう。
物件探しから始めるのもよいですが、先に融資条件を把握しておくのがおすすめです。
というのも、事前に融資条件を知っておくことで、効率よく物件探しが行えるからです。
例えば、自己資金が1,000万円の方が1億円の良さそうなアパートを見つけても、7,000万円までしか融資が出なければ物件を買えません。
7,000万円までローンを組めることが分かっていれば、物件探しの範囲を絞り込めます。
さらには、「本当は低金利でローンを組めたのに、高金利のローンを組んでしまった」という失敗も防げます。
事前に不動産投資用ローンの融資条件を確認する方法は以下のとおりです。
・銀行のHPや最新の融資情勢を発信しているYouTube、ブログなどで確認
・不動産投資コミュニティに入り、投資家同士で情報交換
・投資用アパートを取り扱う会社に確認
・HPなどに情報がない地元の地銀や信金は仮の物件を持ち込んで融資相談
銀行に仮の物件を持ち込んで相談する際も、資料等を作り込んで真剣に臨まないと門前払いにあう可能性があります。
軽すぎる気持ちで銀行面談には臨まないようにしましょう。
Point 2. 高値掴みをしない
高値掴みはアパート投資で最も避けたい失敗の1つです。
当然ですが、アパートの購入金額は決済後に変更できません。
そのため、高値掴みをしてしまうと売却をしても赤字の期間が長く続きます。
損切り売却や自己破産をしなければ、物件を手放せません。
また、家賃を無理やり引き上げないとキャッシュフローも悪くなります。
無理やり引き上げた家賃は下落しやすく、入居もなかなか付きません。
高値掴みをした時点で、数千万円単位の損失が確定することもよくあります。
高値掴みへの対策は以下の3つです。
| 対策法 | 詳細 |
| 相場利回りを把握する | 類似物件(築年数、エリアなどが近いアパート)の利回りをポータルサイトや業者の資料などで10件程度比較します。 比較できる物件が少ない場合は、築年数やエリアの範囲を広げて比較件数を増やします。 家賃を上げる余地がなく、明確に利回りが低い場合は高値掴みの可能性が高いです。 |
| 家賃相場を把握する | 類似物件の1部屋や1坪あたりの家賃を比較します。 高すぎる家賃が設定されている場合は高値掴みの恐れがあります。 |
| 必要なCFから判断する | 自分が必要とするCFに達しているかで適正価格か判断します。 考え方やエリアによって大きく違いがありますが、一般的に物件価格に対して2%のCFがあれば優良物件とされます。 |
相場観はすぐに身につかないので、まずは自分が狙うエリアの物件の収支計算を数多くこなしましょう。
相場観が身につくと、条件の良い物件にすぐ反応ができます。
Point 3. エリアの賃貸需要や災害リスクを正確に調査する
立地もアパート購入後に変えられない要素のため、細心の注意を払う必要があります。
賃貸需要のないエリアを選んでしまうと、空室で想定していた賃料が得られません。
また、銀行から融資が受けにくいエリアもあります。
エリアの選定ミスがアパート投資の失敗に直結すると言ってよいでしょう。
エリア選定で気をつけるべきポイントは以下のとおりです。
| リスクのあるエリア | 詳細 |
| 駅徒歩11分以上の立地 | 多くの方は駅徒歩10分以内で賃貸物件を探すため、11分以上の物件は検索対象から外れやすくなります。 SUUMO検索の駅徒歩分数は、1分・5分・7分・10分・15分で区切られるため、7分以内だとさらに理想的です。 |
| 人口減少が続いているエリア | 人口減少が続くと将来的な空室リスクが増します。 人口の増減は、内閣府・経済産業庁が提供しているRESASの人口マップなどで確認可能です。 |
| 同タイプの部屋が供給過多に なっているエリア | 部屋探しをしている人の数(需要)より、部屋数(供給)が多いと空室リスクが高まります。 近隣アパートの間取りや広さなどの需給のバランスは、LIFULL HOME’Sの見える!賃貸経営などで確認できます。 検索件数の割合より掲載件数の割合が「少ない」部屋タイプのアパートが狙い目です。 |
| 移転リスクのある工場や大学に賃貸需要が依存しているエリア | 特定企業の工場や大学の地方キャンパスなどは業績悪化や都心回帰による移転リスクを抱えています。 賃貸需要の要となっていた施設が移転すると、空室リスクの高いエリアになります。 |
| 駐車場がマストなエリア | 車移動がマストなエリアで、駐車場のないアパートを購入してしまうと入居付けが困難になります。 |
| ハザードマップで災害リスクの高いエリアに位置している | ハザードマップとは、各地方自治体が発行している水害時などの想定被害範囲が記載された地図データのことです。 被害想定の大きいエリアでは、購入時・売却時に融資が出にくいことがあります。 |
上記のポイントを押さえながらエリアの賃貸需要を調べることで、アパートの空室リスクなどを下げられます。
Point 4. 違法建築物でないか確かめる
投資用アパートを購入する際には、建築基準法や条例に違反していないか確認しましょう。
違法建築されたアパートには下記のようなデメリットがあります。
・売買時に融資が付きづらい、融資を組めても条件が悪いことが多い
・災害などに対する入居者の安全性が確保できない
・行政指導が入り、使用禁止になるリスクがある
こうしたデメリットがある分、安く物件を購入できる可能性はありますが、経験値のない方にはおすすめできません。
代表的な違法建築の例についてまとめます。
| 違法建築例 | 詳細 |
| 建ぺい率オーバー | 建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た際の面積)の割合のことです。 建築面積120㎡÷敷地面積200㎡=建ぺい率60%といった計算式で算出されます。 建ぺい率は地域ごとに上限が異なり、上限を超えてしまうと違法物件とみなされます。 |
| 容積率オーバー | 容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。 延べ床面積200㎡÷敷地面積100㎡=容積200%といった計算式で算出されます。 地域や前面道路の広さなどによって上限が異なります。 |
| 採光不良 | 建築基準法では、居室面積の1/7以上の開口部(窓)を設置することが義務付けられています。 この基準を満たしていなければ、違法物件とされます。 |
| 違法増築 | 10㎡以上の増築をする際には、建築確認申請が必要です。 こちらを怠ると違法増築となります。 |
| 接道義務違反 | 接道義務とは、建物が一定の幅以上の道路に面していなければならないという建築基準法の規定です。 具体的には、都市計画区域内に建てられた建物は、原則幅員4m(6mの場合も)以上の道に2m以上接していなければなりません。 面している道路の幅員が4mに満たない場合は、道路の中心から2mのラインまで敷地の縁を後退させる必要があります。 |
違法建築物かどうかを調べる方法としては、以下の2つがおすすめです。
| 調査方法 | 詳細 |
| 確認済証・検査済証がないか 調べる | 建物を新築する際には、違法性がないか行政のチェックが入り、問題がなければ確認済証が発行されます。 工事が完了した後にもチェックを受けてOKであれば、検査済証が発行されます。 中古物件だと検査済証がない場合が多いです。 |
| 増築登記がされているか調べる | 10㎡未満の増築でも不動産登記が必要で、登記上の面積を修正しなければなりません。 増築をしているのに、登記をしていない場合は注意が必要です。 |
「違法建築=儲からない」というわけではありませんが、十分な知識をつけてから購入を検討するとよいでしょう。
Point 5. ランニングコストを十分に加味する
アパートを購入する際には初期費用だけでなく、ランニングコストも細かく計算しなければなりません。
不動産会社から提示されたアパート収支は、コスト計算が不十分なこともあるからです。
ポジティブすぎる試算を鵜呑みにして、投資が破綻してしまうケースは珍しくありません。
自分の身を守るためにも、アパート収支は自力で計算する必要があります。
収支計算の際に、特に気をつけるべきポイントは以下のとおりです。
| 注意ポイント | 詳細 |
| 空室率 | エリアによって空室率は大きく異なります。 地方物件なのに、想定入居率が首都圏と同程度の95%では実際の収支と合いません。 以下のような方法で空室率を想定します。 ・SUUMOなどで類似物件の空き状況を調べる ・売主や管理会社に過去の空室状況や入金明細を確認する ・実際に現地へ赴き、類似物件の空室状況を調べる ・近隣賃貸仲介会社にどれくらいの空室率になりそうか聞いてみる |
| 広告料 | 入居付けに必要な広告料もエリアや物件需要によって大きく異なります。 首都圏であれば広告料は賃料の0~1ヶ月で済むことが多いですが、地方では3~4ヶ月分の広告料が必要なこともあります。 管理会社や近隣の賃貸仲介会社にどのくらいの広告料が必要か事前にヒアリングするのがおすすめです。 |
| 修繕費 | 前述したとおり、アパートを所有していると設備や建物の修繕費がかかります。 賃料が安くても高くても、修繕費の金額は変わりません。 そのため、賃料が安いエリアの方が収入に対する修繕費の負担が大きくなります。 また、賃料の7~10%は修繕用に積み立てると、突発的な修繕にも備えやすいです。 築20年ごろに多額の修繕費がかかることが多いので、修繕履歴も事前に確認しましょう。 |
| 管理委託料 | 入居者対応や建物管理を不動産会社に依頼する際の手数料です。賃料の3~5%で設定されるのが一般的です。 |
| 税金 | アパート投資を行う際には、固定資産税や所得税がかかります。賃料の5~10%ほどの税金がかかることが多いです。 |
これらを合計すると満室時の総賃料に対して20~30%ほどのランニングコストが発生します。
アパート管理会社の選び方8選
アパート投資で大きな失敗を防ぐために、賃貸管理業務はプロの管理会社に委託するのも1つの手です。
ただし、管理会社選びを失敗すると、空室期間が長くなる・ランニングコストが上がるといったリスクが生じます。
そこで、こちらでは管理会社選びに失敗しないためのポイントついて解説します。
選び方は以下の8つです。
選び方① 中古アパートはそのまま引き継ぐ
選び方② 客付け力
選び方③ 1人当たりの担当戸数
選び方④ 管理と仲介が棲み分けされているか
選び方⑤ 当たり前の報連相ができるか
選び方⑥ 修繕費用が高すぎない
選び方⑦ 清掃や点検を適切に実施している
選び方⑧ 管理委託料が相場ズレしていないか
選び方① 中古アパートはそのまま引き継ぐ
大きな問題がなければ、元々管理会社に委託された物件はそのまま引き継ぐのが無難です。
管理をしている間に発生したトラブルや入居付けのデータなどが元々の管理会社には蓄積されています。
いきなり新しい管理会社に切り替えると、引き継ぎがうまくいかず、トラブルが起こりやすいです。
はじめは、既存の管理会社から今までトラブルなどの情報を教えてもらうとよいでしょう。
既存の管理会社にトラブルが多いなら、自分に経験が蓄積されたタイミングで別会社に切り替えるのも1つの手です。
選び方② 客付け力
ここでの客付け力とは、空室をすぐに埋める力のことです。
物件が良くても管理会社の客付け力が低いために、収支が悪くなっているケースもあります。
客付力をチェックするためのポイントは以下の7つです。
| 対策法 | 詳細 |
| ①囲い込みをしない | 囲い込みとは、入居付けを任された不動産会社が他社に物件情報を公開せず、自社だけで入居付けしようとする行為です。 オーナーと入居者の双方から報酬を受け取ることを目的に行います。 自分の部屋が紹介される機会が減り、空室が長引く恐れがあります。 REINSやATBBといった不動産業者専用サイトにも物件を掲載しているか確認しましょう。 |
| ②掲載画像が充実している | 多くの人は家賃などの金額+物件の画像を見て問い合わせをするか判断します。 ポータルサイトの掲載枚数が少なかったり、見た目の悪い写真ばかりなら注意が必要です。 もし、自分がキレイな室内画像などを持っていれば、管理会社に提供しましょう。 |
| ③オンライン化を積極的に進めている | 近年はITANDI BBやいい生活Squareといったオンラインで内見から申し込みまで行えるサービスが充実しています。 手間が減るので、まずITANDI BBから物件検索をする賃貸仲介会社の営業マンも増えました。 必須ではありませんが、プラスに捉えられる項目です。 |
| ④賃貸仲介会社の負担にならない対応ができている | 管理会社の印象の悪さが原因で、仲介会社が物件を紹介しないこともあります。 ・電話対応がよい ・内見用の鍵をわざわざ管理会社まで取りに行かなくてよい ・いちいち管理会社が内見に立ち会わなくてもよい ・契約書類は管理会社が作成し、仲介会社は作成しなくても良い この辺りに注目しましょう。 |
| ⑤余計な手数料を請求しない | 管理会社によっては、賃貸契約の際に余計な手数料まで入居者に請求することがあります。 ・契約事務手数料 ・除菌消臭代 ・消化器代 など 上記のような費用を請求していると、入居者・賃貸仲介会社に悪い印象を与えます。 |
| ⑥業者営業をしている | 物件近くの不動産会社に訪問・メールなどで客付け依頼をかけている管理会社の営業力は高いです。 待ちの姿勢の管理会社の方が多いので、空室対策として大きな差別化を図れます。 |
| ⑦独占状態を築き上げている | エリアによっては、1社がほぼ全ての入居窓口になっていることがあります。 そうした場合は、その会社に管理を任せるのがよいでしょう。 |
客付けができなくて困るのは自分なので、当事者意識を持ってチェックしましょう。
選び方③ 1人当たりの管理戸数
管理戸数が多いのは、安心感に繋がりますが、1人当たりの担当戸数が多すぎる場合は注意が必要です。
業務負荷がかかりすぎて、ミスや漏れが頻発する恐れがあります。
管理業務は、入居のトラブル対応や清掃業者手配、契約手続きなど多くの業務が存在します。
あまりにも多くの戸数を担当してしまうと、抜け漏れや雑な対応に繋がりかねません。
目安としては、1人で1,000戸以上の管理戸数を抱えていると、業務過多になっている可能性が高いです。
管理戸数の多さだけで管理会社選びをするのは避けましょう。
選び方④ 管理と仲介が棲み分けされているか
1人の担当者が管理業務と仲介業務を兼任している不動産会社に管理を任せるのは、あまりおすすめできません。
※仲介業務とは、他社の物件の入居付けを仲介する業務のことです。
仲介と管理を兼任していると、一人当たりの管理戸数が多い場合と同様に、業務過多で管理の質が下がる恐れがあります。
特に仲介業務は営業ノルマなどがあるので、管理よりも優先度が高いことも多いです。
どの程度管理に専念できるか事前にチェックしましょう。
選び方⑤ 当たり前の報連相ができるか
オーナーと基本的な報告・連絡・相談(報連相)ができない不動産会社に管理を委託するのは危険です。
基本的な報連相とは以下のようなものを指します。
・退去申請があった際の報告
・賃貸募集条件の相談
・修繕を行うかの相談
・入居申し込みの報告と相談
・入居更新の連絡
こうしたオーナーにとって重要な情報の報連相ができない管理会社も稀に存在します。
ひどいケースだと、空室が出たにも関わらずオーナーに報告しないまま数ヶ月が経過していたことがありました。
やりとりをする中で、「社会人として信用できない」と感じたら契約を見送るのがおすすめです。
選び方⑥ 修繕費用が高すぎない
自分で修繕業者の手配をしない場合は、管理会社から修繕業者の見積もりが送られます。
その見積もりが相場よりもかなり高い場合は、注意が必要です。
管理会社によっては、修繕費用に管理会社の利益分が大きく上乗せされているかもしれません。
多少の上乗せがあっても、その他の管理業務の質が高ければ許容してよいでしょう。
ただ、相場より倍額以上の費用などであれば、アパートの収益性に致命的な悪影響を及ぼします。
自分で修繕会社を探す・管理会社を変えるといった対策が必要です。
実際に、自分で修繕業者の相見積もりを取り、修繕費用が半額以下に下がるケースがありました。
選び方⑦ 清掃や点検を適切に実施している
建物の清潔感や共用設備の不具合の有無は、入居率にも影響する要素です。
例えば、ゴミ置き場や廊下にゴミが散らかってる・ライトが点灯しないなどの理由で入居が見送られることもあります。
定期的にアパートの管理状態の報告があり、設備のメンテナンスを行うか相談してくれる管理会社を選べると安心です。
管理委託の相談する際に、どのように清掃や点検を行うか確認しましょう。
選び方⑧ 管理委託料が相場ズレしていないか
管理業務を不動産会社に委託する際には、賃料の何%といった具合に管理委託料が発生します。
委託料の高い・安いよりも管理の質の方が重要ですが、相場価格から大幅にずれている場合は注意が必要です。
管理委託料の相場は、首都圏が賃料の3%で、地方は賃料の5%ほどです。
この水準を大きく超える場合、必要以上に管理委託料を払っている可能性が高いので、管理会社の切り替えも検討しましょう。
融資を受ける銀行の選びのコツ3選
アパート投資と融資は切っても切り離せない関係です。
投資の成否は、融資条件によって左右されるといってもよいでしょう。
融資の引き方に絶対の正解はありませんが、取り組みのコツが3つあるので紹介します。
コツ① アパートローン→プロパーローンの順番で借りる
コツ② 借入があると融資が受けれられない銀行から融資を受ける
コツ③ 融資難易度が高い銀行から順番に融資を受ける
コツ① アパートローン→プロパーローンの順番で借りる
アパート投資で受けられる融資には、主に「アパートローン」と「プロパーローン」の2種類があります。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
| アパートローン | プロパーローン | |
| 概要 | 投資目的でアパートやマンションを購入する方向けのローン。 金融機関と保証会社が審査を行い、返済が滞った際には保証会社が弁済を行います。 パッケージ型の商品で、融資条件が明確です。 | 個々の案件に応じて融資可否が決まるローン。 保証会社を介さず、金融機関の独自の審査を行います。 オーダーメイド型の商品で、個々の融資条件は不明確です。 |
| メリット | 融資を受けるための基準が明確で、条件を満たせばローンが通りやすいです。 融資条件は、銀行のHPや最新の融資情勢を解説したYouTube動画などで確認できます。 | 借入があっても優れた事業性などを証明できれば融資を受けられます。2棟目、3棟目と規模拡大ができます。 |
| デメリット | 基準を満たさなければ、融資を受けられません。 借入額が多くなると融資を受けにくくなります。 | アパート投資の実績や事業性を自分自身がプレゼンしければなりません。 融資難易度は高く、1棟目で融資を受けるのは難しいです。 |
アパート1棟目からプロパーローンで融資を受けるのは不可能ではありませんが、非常に困難です。
まず、アパートローンで一棟目を購入し、実績を積んでからプロパーローンにチャレンジするのがよいでしょう。
コツ② 借入があると融資が受けれられない銀行から融資を受ける
融資の審査基準として、「年収〇〇倍まで」といった限度額が決まっているものがあります。
有名なのが、オリックス銀行の年収の10倍までという条件です(2025年現在)。
別の銀行でローンを組んでいると、融資限度額の決まっている銀行から融資を受けるのは難しくなります。
そのため、「限度額のある銀行→限度額のない銀行」といった順番で融資を受けると、融資枠を無駄なく使えます。
アパート投資は融資ハードルが高いからこそ、融資枠を効率よく活用しましょう。
コツ③ 融資基準が厳しい銀行から順番に融資を受ける
審査は厳しいものの、融資条件の良い銀行から相談するのも1つの手です。
というのも、先に借入れがある状態だと、そうした銀行の審査ハードルがさらに上がるからです。
最初に審査の厳しい銀行に相談し、徐々に難易度を下げていくことで、融資条件面での損が無くなります。
融資基準の厳しい銀行を上から順に並べたのが以下の表です。(2025年現在)
| 銀行の種類 | 概要 |
| メガバンク系(三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行) | ほぼ融資を受けられる人はいないレベルの難易度。 ほとんどの方は、選択肢から外してよい銀行です。 |
| 準メガバンク(りそな銀行) | 1億円以上の金融資産があれば融資対象になりうる銀行。 |
| 地方銀行①(千葉銀行、横浜銀行、東日本銀行など) | アパート投資への融資が積極的なものの審査が厳しめな地方銀行。 年収1,000~1,500万円以上、金融資産として2,000~5,000万円が求められることが多いです。 |
| 地方銀行②(スルガ銀行、静岡銀行など) | 比較的融資を受けやすい地方銀行。 年収700~1,000万円以上、金融資産は1,000万円以上あるのが望ましいです。 |
| ネットバンク系(オリックス銀行、auじぶん銀行など) | アパート投資に積極的に融資してくれる銀行。 年収700万円以上、金融資産が500~1,000万円以上あると理想的です。 |
| 地方銀行③(香川銀行、滋賀銀行、徳島大正銀行など) | あまり年収が高くない方でも相談ができる銀行。 融資可能額は5,000万円以下の場合が多いです。 必要年収は300~500万円以上など。 |
| 信金系(各地域ごとに異なる) | プロパーローンとして融資の可否が決まる金融機関です。 個々の案件ごとに融資額などが大きく異なります。 |
| ノンバンク系(三井住友トラストローン&ファイナンスなど) | 金利が高い・ローン期間が短いなどのデメリットはありますが、他の銀行がNGでも審査が通りやすい金融機関です。 ローンのない自宅などを担保に入れると融資額が伸びたりします。 |
メガバンクや準メガバンクから融資を受けられる方は稀なので、地方銀行やネット銀行からまず相談してみるとよいでしょう。
また、審査基準は時期によって変わるので、常に最新の融資情勢をチェックしておくのがおすすめです。
アパート投資のよくある質問
こちらでは、アパート投資にまつわるよくある質問についてQ&A形式で解説します。
よくある質問は以下の6つです。
Q1. 新築と中古どちらの方がよい?
Q2. 確定申告は必要?経費として認められるものは?
Q3. 空室リスクを下げるためにはどうしたらよい?
Q4.家賃滞納があったらどうすればよい?
Q5.利回りは何%必要?
Q6.自分で住める?
Q1.新築と中古どちらがよい?
A.投資目的などによって異なります。
アパート投資では、新築でも中古でも成果を出している方がいるので、どちらが正解・不正解ということはありません。
それぞれの特徴やご自身の状況を加味して、投資の選択を行うことが重要です。
| 新築アパート投資に向いている方 |
| ・修繕などの手間やトラブルを回避して安定経営をしたい方 ・リターンが多少下がってもリスクを抑えることを重視したい方 ・長期融資やフルローンに近い融資を受けたい方 |
収益性が低すぎると、そもそも投資として成り立たない新築物件もあるので注意が必要です。
「土地建物プラン付き」や「土地から新築」などの建築リスクを取ることで、リターンを上げる選択肢もあります。
| 中古アパート投資に向いている方 |
| ・修繕などのリスクを取ってもリターンを取りに行きたい方 ・入居実績を確認してから物件を購入したい方 ・融資枠があまりないので、物件購入価格を抑えたい方 |
新築では出せない高利回りを狙うのであれば、中古アパート投資がおすすめです。
ただし、築年数に伴う様々なリスクを考慮して、物件選定を行う必要があります。
Q2.確定申告が必要?経費として認められるものは?
A.確定申告や決算はマストです。
アパートを個人や法人名義で所有した際は、毎年の確定申告や決算をしなければなりません。
自分で帳簿付けをするか、税理士に委託して申告を行います。
アパート投資の経費として認められる主な項目は、以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 税金系 | ・登録免許税 ・印紙税 ・不動産取得税・固定資産税 ・都市計画税 など |
| ローン系 | ・融資事務手数料、保証料・返済金利(赤字の場合は、土地の金利のみ) |
| 管理・運営系 | ・広告費 ・管理委託料 ・インターネット設備費用・修繕費 ・共用部の電気、水道代 など |
| 保険系 | ・火災保険料、地震保険料 |
| 減価償却費 | ・建物や設備の減価償却費 |
| その他費用 | アパート投資に関わる費用のみ。私用のものは脱税です。 ・交通費 ・新聞図書費 ・消耗品費 ・専門家への報酬 ・立ち退き費用 ・交際費 など |
営業トークで「投資用不動産を持つと全ての領収書を経費にできる」と説明する方もいますが、多くの場合は脱税に該当します。
特に個人名義で物件を所有している場合は、経費として認められる範囲が法人名義より狭まるので注意しましょう。
Q3.空室リスクを下げるにはどうしたらよい?
A.立地・家賃・間取り・設備・広告費などを意識しましょう。
空室リスクはアパート投資で最も避けたいリスクの1つです。
空室対策には、立地・家賃・間取り・設備・広告費を物件選定時から意識するのが有効です。
| 対策項目 | 詳細 |
| 立地 | そもそも賃貸需要がない立地を選ぶと空室対策はかなり困難です。 立地は後からの変更が一切利きません。 土地の賃貸需要を調査した上で、物件選定を行いましょう。 |
| 家賃 | 相場と比較して家賃が高すぎると入居が付きません。 賃料相場はSUUMO賃貸経営サポートなどで確認できます。 |
| 間取り | 供給過多だったり、需要のない間取りや広さでも入居は付きにくいです。 LIFULL HOME’Sの見える!賃貸経営や近隣の賃貸仲介会社への聞き取り調査で需要のある間取りを確認しましょう。 |
| 設備 | 人気の設備があることで入居付けをしやすくなります。 無料インターネットや宅配ボックス、モニター付きインターホンなどは後から設置できます。 家賃アップの効果などもあるので、積極導入するのがおすすめです。 |
| 広告費 | 賃貸仲介会社へ支払う広告費も入居付けを行う上で重要な項目です。 近隣の物件には広告費があるのに、自分の物件だけ広告費がないと、仲介会社に紹介されにくくなります。 入居がつかなければ広告費を付ける・金額を上げるなど選択肢も検討しましょう。 |
Q4.家賃滞納があったらどうすればよい?
A.そもそも家賃保証会社をつければ滞納リスクを避けられます。
家賃滞納があると、督促→緊急連絡先や連帯保証人への連絡→内容証明郵便での督促→裁判といった面倒な手続きが必要です。
こうした手続きは家賃保証会社を賃貸借契約時につけることで回避できます。
家賃保証会社とは、入居者の家賃滞納があった際に家賃の立て替えをしてくれる会社です。
滞納者への催促なども家賃保証会社が行います。
また、利用に必要な保証料は基本的に入居者が支払うため、オーナーには金銭的なデメリットもありません。
国土交通省によると約8割の賃貸借契約で、家賃保証会社が利用されています。
積極的に家賃保証会社を活用して、滞納リスクを回避しましょう。
Q5.利回りは何%必要?
A.ケースバイケースですが、利回りのみで判断するのは危険です。
立地や築年数によって求められる利回りは大きく変動するので、一概に何%と断言するのは難しいです。
ただ、高値掴みを防ぐために相場の利回りは必ずチェックする必要があります。
ポータルサイトや不動産会社のメール配信などで相場を掴み、明らかに良い条件のアパートには反応できるようにしましょう。
一方で、高利回りばかりを重視するのも危険です。
空室リスクや家賃下落リスクなど踏まえた上で、正確な利回りを計算する必要があります。
また、自分の投資目的を果たせるのであれば、利回りにこだわり過ぎる必要もありません。
いくらまで利益が出れば十分なのかも事前に計算しましょう。
Q6.自分で住める?
A.自分がアパートに居住することは可能です。
自分が所有した物件なので、空き部屋があれば自分や親族の居住はできます。
賃貸併用住宅として、自宅とアパートがセットで売られているケースもあります。
一方で、オーナーが同じアパートに住んでいると、ストレスを感じる入居者は少なくありません。
その結果、入居率が下がる可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
この記事の内容をまとめます。
・アパート投資に成功すれば潤沢なキャッシュフローや売却益が得られる。
・レバレッジ効果や相続対策になるなどのメリットがある。
・アパート投資を始めるには、多額の自己資金が必要な場合が多い。
・運営費の計算や高値掴みをしないための分析力が必要。
・融資を受けるための情報量や行動力も重要。
・アパートの管理を委託することで手間を抑えられる。
アパート投資は、深い知識や自己資金など必要な要素が多く、簡単に始められる投資ではありません。
その分、諦めずに挑戦できればチャンスが広がる投資ともいえます。
十分に知識を蓄えた上で、ぜひチャレンジしてみてください。
また、アパート投資を成功させる上で重要なのは、最新の情報やノウハウです。
東京大学卒で不動産投資家の小原正徳さんのYouTubeチャンネルでは、経験に基づくノウハウやトレンドについて学べます。
説明がわかりやすく、投資初心者でも見やすい解説動画が多いので、ぜひ一度視聴してみてください。
小原正徳さんのYouTubeチャンネルはこちら